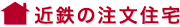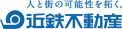近鉄の家づくり
近鉄の注文住宅(奈良県) > 近鉄の家づくり > 補助金制度の紹介
補助金制度の紹介
国の補助金
新築住宅を建築される際に、要件に該当すれば、国から補助金が受けられる場合がございます。事前に申請が必要な場合もございますので、新築住宅を建築をされる前に一度ご確認されてはいかがでしょうか。
- こどもみらい住宅支援事業
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図る制度です。
対象の住宅と補助金額
次の①~③のいずれかに該当する住宅を対象とします。 いずれも、住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)の住宅。
①ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready 又は ZEH Oriented 【補助額100万円/戸】
②高い省エネ性能等を有する住宅【補助額80万円/戸】
次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅を対象とします。
a) 認定長期優良住宅
b) 認定低炭素住宅
c) 性能向上計画認定住宅③一定の省エネ性能を有する住宅【補助額60万円/戸】
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
補助対象期間
①工事請負契約
2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から2022年10月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したもの ※一定の省エネ性能を有する住宅は、2022年6月30日までに工事請負契約を締結したものに限ります。
②建築着工
別途定める事業者登録を行った後以降(2022年1月11日)
※本事業については、当社(近鉄不動産)が所定の手続きにより「補助事業者」としての登録を受ける必要があります。登録のない事業者との契約をしたとしても、「こどもみらい住宅支援事業」補助対象外となり、この制度を利用することができません。当社は、2022年1月11日に事業者登録が完了し、「こどもみらい住宅事業者」として登録されていますので、この制度を利用することができます。③基礎工事の完了
建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2023年3月31日)
申請方法・申請期間
①申請方法
新築住宅の建築事業者が、新築住宅の建築主の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請および交付を受ける。ただし、交付された補助金は住宅取得者に還元される必要があり、申請にあたっては還元方法について、予め両者で同意を行う。
②申請期間
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年3月31日
※工事の完了後に申請。
※申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表。
※予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、申請日が当該締め切り日に近い申請について、補助額 から減じて、補助金を支払う場合があります。詳細は「こどもみらい住宅支援事業について」をご覧ください。
税金制度
新築住宅を建築した際に、要件を満たす場合に税金の優遇を受けることができます。申請には手続きが必要ですので、ご注意ください。また、お住まいの地域からの補助金も一緒に受けられる場合がございます。
- 住宅ローン減税
制度の概要
床面積が50㎡以上の住宅を購入するために金融機関から10年以上のローンを借入した場合に、一定の要件を満たせば年末残高の0.7%が13年間に渡って、所得税額から控除される制度です。所得税から控除しきれない場合は、個人住民税から最大97,500円が控除されます。(年収が2,000万円以下であることが条件です。)
減税される金額
住宅 居住年 借入限度額 控除率 控除期間 認定住宅※1 2022~2023年 5,000万円 0.7% 13年 〃 2024~2025年 4,500万円 0.7% 13年 ZEH水準省エネ住宅 2022~2023年 4,500万円 0.7% 13年 〃 2024~2025年 3,500万円 0.7% 13年 省エネ基準適合住宅 2022~2023年 4,000万円 0.7% 13年 〃 2024~2025年 3,000万円 0.7% 13年 その他の住宅※2 2022~2023年 3,000万円 0.7% 13年 〃 2024~2025年 0円 0.7% 13年 ※1 認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいう。
※2 省エネ基準を満たさない住宅。2024年1月以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。
2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024年・2025年に入居する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年。対象となるローン
返済期間が10年以上のローン
対象となる住宅の要件
・取得の日から6カ月以内に入居すること
・床面積が50㎡以上で、2分の1以上が自己居住用であること(合計所得金額1,000万円以下の方の床面積要件を40㎡以上に緩和)申請方法
入居した年の翌年の確定申告時に申請します。申請方法は、税務署に必要書類を提出します。
2年目からは、勤務先にローンの残高証明書を提出し、年末調整で控除を受けることができます。(給与所得者の場合)※詳細は、こちらからご確認ください
- 相続時精算課税制度の特例
制度の概要
この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に手続きが必要です。
対象者
[贈与者]満60歳以上の親又は祖父母
[受贈者]20歳以上の子又は孫(令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」)
対象住宅
・床面積が 50㎡以上240㎡以下の住宅
・床面積の2分の1以上が住居用
非課税限度額
累計2,500万円
贈与税額
累計額を超えた部分に対し、一律20%が贈与時にかかります。
※基礎控除の110万円とは併用できませんのでご注意ください。
※詳細は、こちらからご確認ください.- 贈与税の非課税措置
制度の概要
父母や祖父母などからの贈与により、住宅を取得した際に、一定の要件を満たす場合は、
一定の金額については贈与税が非課税となります。
この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが必要です。対象者の範囲
贈与者:父母・祖父母などの直系尊属
受贈者:国内に住所があり、その年の1月1日において18歳以上の 子・孫(所得:2,000万円以下)。
贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅を取得をすること。対象住宅
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
(住宅取得等資金贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積が40㎡以上240㎡以下に緩和)
非課税枠
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税
※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋
(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること、
または③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)
※基礎控除の110万円とは併用できます。
※詳細は、こちらの「贈与税の非課税措置」からもご確認ください。